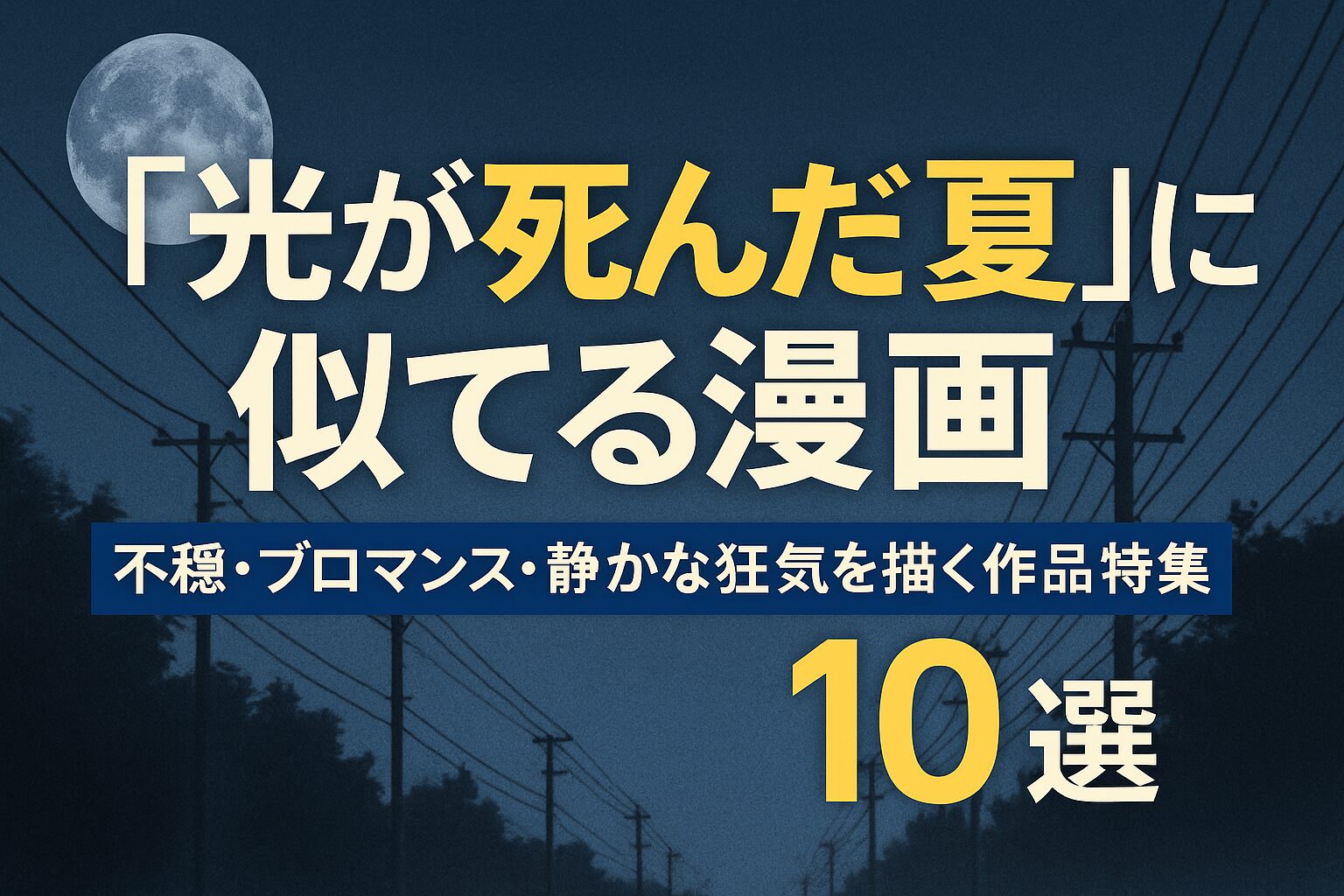『光が死んだ夏』の独特な“日常に潜む違和感”や“静かに広がる狂気”に引き込まれたあなたにぴったりの漫画を紹介します。
この記事では、雰囲気やジャンルごとに『光が死んだ夏』に似た作品を厳選。
不穏さ・ブロマンス・怪奇・心理的恐怖といった要素が共鳴する作品を、読者の体験と照らし合わせながらご提案します。
- 『光が死んだ夏』に似ている漫画の特徴と選び方
- ジャンル別に楽しめる類似作品の魅力や読後感
- 不穏・ブロマンス・閉鎖空間など共通テーマの解説
① 不穏×静謐なホラー:閉塞的日常が怖い
『光が死んだ夏』が描くのは、一見穏やかな日常にじわじわと染み込む狂気です。
このセクションでは、そんな作品と共通する“静かに広がる恐怖”や“閉鎖的な舞台”を軸に、似たような読後感を味わえる漫画を紹介します。
人間関係の緊張感や不安定さが巧みに描かれた物語に心惹かれる方におすすめです。
・『ひぐらしのなく頃に』
昭和の寒村・雛見沢を舞台にしたこの作品は、日常の裏に潜む恐怖と狂気を描いています。
最初は穏やかな日常が繰り広げられますが、次第に登場人物たちの言動が不穏な兆しを見せ始める構成は、『光が死んだ夏』と非常に似ています。
「この世界には何かがおかしい」という空気感が徐々に読者を追い詰めていくのが魅力です。
・『変な家』
「間取りが怖い」という新しい視点からホラーを展開する『変な家』は、一見普通の暮らしに潜む異常性が際立ちます。
物理的な構造(間取り)を通じて違和感を炙り出す手法は、視覚的にも心理的にも“日常の異常”を表現しており、『光が死んだ夏』のようなじわじわくる不安感があります。
「気づいた時にはもう後戻りできない」という構成が、読者の恐怖心を増幅させていきます。
まとめ:不穏で静かな狂気を味わいたい人に
どちらの作品も共通しているのは、恐怖を爆発的に見せるのではなく、空気に染み込ませるように描いている点です。
『光が死んだ夏』のように、“閉塞した空間での不穏な変化”や“誰にも言えない違和感”を体感したい方には、まさにぴったりの作品です。
静謐な世界のなかでじわじわ広がる恐怖を、ぜひ体感してみてください。
② “すり替わり”や“他者への侵食”テーマ
『光が死んだ夏』の最大の特徴のひとつは、「光」が“光ではない何か”にすり替わっているという恐怖です。
このような、“誰かの中身が他の何かに置き換わっている”というテーマは、人間の根源的な不安を刺激します。
他者に侵食される恐怖や、自分が信じていた人が変わってしまう恐怖にフォーカスした漫画をご紹介します。
・『ぼくらの』
14人の少年少女がロボットの操縦者として選ばれ、自らの命と引き換えに戦うSF作品です。
物語の根底には、“他者の命と意識の交代”という構造があり、『光が死んだ夏』における“ナニカ”と入れ替わる恐怖と呼応します。
「自分の知らないうちに、自分が誰かになっている」という喪失感と恐怖が深く心に残ります。
・『ミギとダリ』
養子として迎えられた双子の少年が、ひとつの人間になりすまして生活するという異様な設定の本作。
彼らが交代しながら“ひとりの子ども”としてふるまう姿は、「人間の仮面をかぶる異物」という意味で、『光が死んだ夏』に非常に近い空気をまとっています。
一見普通に見えるけれど、本当は何かがおかしいという不穏な構成が魅力です。
まとめ:“存在のすり替わり”にぞっとする感覚を
このような作品では、“人間とは何か”や“自我とは何か”という問いが根底にあります。
大切な人が大切な人でなくなる怖さを感じた読者には、このジャンルの作品が強く刺さるでしょう。
正体不明な“異物”と共存する恐怖を、もう一度別の形で味わってみてください。
③ 男同士の異質な絆・ブロマンス要素
『光が死んだ夏』のもう一つの魅力は、夕暮と“光らしきもの”の間にある言葉にできない繋がりです。
それは友情とも、愛情とも、共依存とも違う、曖昧で異質な絆といえます。
このセクションでは、そんな“男同士の関係性”を軸にしたブロマンス的な漫画をご紹介します。
・『チェンソーマン』
一見ジャンルは異なりますが、デンジと早川アキの関係性や、マキマとの主従のような絆には、暴力と感情が複雑に交錯する人間関係が描かれています。
とくに、「なぜ一緒にいるのか分からないけど、離れられない」という感覚は、『光が死んだ夏』における夕暮と“光”の関係にも似ています。
激しい描写が多い点では方向性が異なりますが、関係性の病理的な側面は共通しています。
・『夏目アラタの結婚』
死刑囚・品川真珠と“偽装結婚”をすることになった夏目アラタの視点で展開する本作。
「理解しがたい相手に惹かれていく心理」は、夕暮が“光でない光”に執着する感情と重なります。
アラタが真珠を「知りたい」「話したい」と思う衝動は、不可解な他者への渇望を描いており、読者に強烈な共感や違和感を抱かせます。
まとめ:言葉にならない感情に触れる
ブロマンス的な関係性は、単なる“仲良し”とは異なり、共鳴、依存、そして恐れといった複雑な感情が交錯しています。
『光が死んだ夏』の本質を、「何かがおかしい関係性」に感じた人にとって、これらの作品は深く刺さることでしょう。
理解できないほど強く惹かれる関係を、別の形でもう一度味わってみてください。
④ ミステリー寄りホラー:普通ではいられない葛藤
『光が死んだ夏』の魅力は、「普通でありたいのに、普通ではいられない」という葛藤にもあります。
それはホラーでありながら、ミステリーのような知的な問いかけを含み、読者を深く引き込む力を持っています。
ここでは、“謎”と“恐怖”が共存する作品をご紹介します。
・『兄だったモノ』
タイトルからして不穏なこの作品は、失踪した兄が戻ってくるところから始まります。
しかしその兄は、かつて知っていた兄ではない“何か”になっており、主人公はその違和感に苦しみます。
家族でさえ信じられないという恐怖と、徐々に明かされていく謎が、心理的ミステリーとしての完成度を高めています。
・『百鬼夜行抄』
妖怪や霊との関わりを描いたオムニバス作品ですが、全体を通して流れるのは、「この世は見えないものに満ちている」という静かな怖さです。
主人公・律が日常のなかで遭遇する怪異は派手さはないものの、不気味さと余韻のある恐怖が『光が死んだ夏』と非常に近い雰囲気を持っています。
事件の真相だけでなく、感情の揺らぎまで丁寧に描く点で、ミステリーとしてもホラーとしても優れた作品です。
まとめ:謎と恐怖が心を揺らす
『光が死んだ夏』の読者が感じたのは、正体不明な“何か”への不信と、身近な人への疑念だったのではないでしょうか。
ここで紹介した作品もまた、“信じたいけど信じきれない”という人間関係の裂け目を突いてきます。
恐怖の中に潜む謎を解き明かすことで、より深く心に刺さる作品体験が得られるでしょう。
⑤ 閉鎖的な舞台で余韻を残す恐怖描写
『光が死んだ夏』は、田舎という閉ざされた舞台で展開されることで、恐怖がより密度を持って描かれています。
このように、外界との断絶による不安感や逃げ場のない構造が、作品の不穏な空気を高める役割を果たします。
ここでは、“閉鎖空間”と“静かに染み込む恐怖”が共存する作品をご紹介します。
・『夏目アラタの結婚』(再掲)
この作品は再掲となりますが、物語の大部分が刑務所という極めて限定された空間で進行する点が注目に値します。
登場人物たちが“逃げ場のない対話”を繰り返すことで、心理的にも閉じ込められていく構造が非常に秀逸です。
アラタと真珠の間に漂う異質な空気は、静かな恐怖と緊張感を見事に生み出しています。
・『ミギとダリ』(再掲)
住宅街という一見開かれた空間でありながら、双子がひとりの人間として生活する密閉感は、まさに“閉鎖的恐怖”の極みです。
登場人物が隠し続ける秘密と、それが少しずつ漏れ出す演出により、読者は常に不安と隣り合わせになります。
特に、「他者の存在によって自分の輪郭が曖昧になる」感覚は、『光が死んだ夏』と深く共通しています。
まとめ:静かな場所ほど恐怖は深まる
逃げ場のない空間で繰り広げられる物語は、心理的に追い詰められる恐怖を極限まで引き出します。
『光が死んだ夏』のように、“どこにも逃げられない”閉鎖感に共鳴した読者には、今回の2作品が特におすすめです。
静かな場所に漂う異物感をじっくりと味わいたい人にこそ、ぜひ読んでいただきたい作品群です。
まとめ:「光が死んだ夏」似てる漫画まとめ
『光が死んだ夏』に惹かれた読者が感じているのは、“静けさの中に潜む異常”や、“日常がじわじわ壊れていく恐怖”といった、感覚的な怖さだと思います。
それは単なるジャンルとしてのホラーではなく、読後にも尾を引くような心理的余韻によって形作られています。
今回ご紹介した漫画は、そのような感情にシンクロしながら、別の角度から恐怖や異質な関係性を描いている作品群です。
- 閉鎖的な舞台での違和感が主軸の『ひぐらしのなく頃に』『変な家』
- すり替わり・侵食を描いた『ぼくらの』『ミギとダリ』
- ブロマンス的な異質な絆が魅力の『チェンソーマン』『夏目アラタの結婚』
- ミステリーホラーとしての深みを持つ『兄だったモノ』『百鬼夜行抄』
それぞれが『光が死んだ夏』と異なる手法で、“誰かが変わってしまった世界”を描いています。
この一覧から気になる作品を手に取り、もう一度あの「静かで異様な夏」の空気に浸ってみてはいかがでしょうか。
「心の奥に残る恐怖」を求める方にとって、きっと新たなお気に入りが見つかるはずです。
- 『光が死んだ夏』に似た漫画をテーマ別に紹介
- 不穏な日常やすり替わりの恐怖を感じる作品群
- 男同士の歪んだ絆や心理ホラーが共通点
- 静かで閉鎖的な空間に漂う異物感がキーワード
- 読後も余韻が残る“静かな狂気”が味わえる
- ホラー×人間関係が交差する物語に注目